 |
月収
(原田ひ香)
図書館83
(911)
84 |
収入も年齢も多岐にわたる6人の女性の連作短編集、でも登場人物がどこかでつながっている。「【月収4万円の66歳】…年金暮らしで貯金を切り崩す毎日に、ある収入源が?【月収8万円の31歳】…専業作家を目指し、不動産投資を始める。【月10万円投資の29歳】…普通の会社員が、親の介護を見越して新NISAを利用。【月収100万円の26歳】…パパ活専業で、20代のうち1億円を稼ぐのが夢!【月収300万円の52歳】…夫の遺産と株式投資で、働かずとも暮らせてはいるが…。【月収17万円の22歳】…元介護士。生前整理の会社を立ち上げる―?」。お金に囚われた人たちの生き様、面白いし考え方が勉強にはなるが、ちょいと現実味が感じられない。
ラストは少しホッとはするけど…。 |
 |
コンビニ兄弟4
(町田そのこ)
図書館82
(910)
83 |
コンビニ兄弟第4巻。店長の除霊騒ぎと、離婚して越してきた女性の話、ヒーローになりたかった男性の話。「①百合は大好きだった夫と別れ傷心の一人暮らしを始めるが、門司港で妙に賑うコンビニを発見する。②舞人はかつてヒーローになりたかった。自分を見失う彼の元に突如訪れた“テンダネス着ぐるみ”を着るバイトが舞い込む。その背後にはテンダネスでバイトをしている同級生との過去から今に繋がる熱い友情があった。」。報われなくてもなぜかホットさせるお話は健在。『ばかって言うのはね、人を傷つけてもそれがわからないひとのことを指すんだよ』
NHKでテレビ化され総合で2026年春、放送スター。乞うご期待! |
 |
神さまショッピング
(角田光代)
図書館81
(909)
82 |
タイトルは“ドクターショッピング(セカンドオピニオンを聞きまくる)になぞらえて”あちこち神頼みをして回ることを指している、8つの短編集。「夫にも誰にも内緒でひとりスリランカへ向かった私が、善き願いも悪しき願いも叶えてくれる神さまに祈るのは、ぜったい誰にも言えないあのこと――。神楽坂、ミャンマー、雑司ヶ谷、香港、モンゴル、サンティアゴ・デ・コンポステーラ、ガンジス川など。どこへ行けば、願いは叶うのだろう。誰もが何かにすがりたい今の時代に、私のための神さまを求める8人…」。世界にはいろんな神様がいるものだ、人が神様にいろんなことを願っているのが面白い、が、サンティアゴ以外はあまり印象には残らなかった。 |
 |
PRIZE
プライズ
(村山由佳)
図書館80
(908)
81 |
賞(prize)という栄誉を獰猛に追い求める作家が主人公、“どうしても直木賞が欲しい”。さぁ、どうなる?「軽井沢に夫と別居して暮らしている作家の天羽カイン48歳。ライトノベルでデビューし3年後、本屋大賞を受賞する。そして直木賞に2度ノミネートをされるが、受賞はできなかった。けれどもう、欲しいのは富ではない。栄誉だ。賞だ。堂々と直木賞を獲って世間に認められたい。彼女はのどから手が出るほど欲しかった直木賞を果たして獲ることができるのか…?」。最後の最後まで目が離せない。作家と編集者、出版社、選考会の模様、裏側がすべて見えて面白かった。 直木賞を決めるのってこういうことなのか、ととても興味深く読んだ。本好きの人は是非読んでほしい。 |

 |
真珠とダイヤモンド上・下
(桐野夏生)
図書館78/79
(907)
80 |
上下合わせて約750ページ、読んでいて辛くなる。「上巻: 1986年代、貧しいながらも東京行きを夢見る短大卒の佳那と、高卒の水矢子は、福岡の証券会社で同期として出会う。佳那は野心的な同期の望月に見込まれ、ある出来事をきっかけに彼と結託し、マネーゲームに身を投じていく。下巻:
望月と結婚した佳那は、ヤクザの愛人の影響で贅沢な暮らしに染まっていく。一方、水矢子は失敗に終わった受験をきっかけに、思いがけない流転の生活を始めることに。バブルに陰りが見え始めた頃、二人の女性の運命は狂い出していく。」。二人は最後まで救われない、もののとらえ方が鋭い著者だからある程度は予想していたがあまりにも救いがない。バブルに浮かれた人間達の行く末…。 |
 |
十戒
(夕木春央)
図書館77
(905)
79 |
この著者は2冊目、『方舟』は怖かったけどこれはそうでもなく普通の犯人捜し(2冊目と言うことで何となく著者のパターンがわかり犯人の予想ができた)。孤立された島で殺人が起こる話。「浪人中の里英が父と共に訪れた伯父の島で、リゾート開発関係者9人のうち1人が殺害される。現場には“殺人犯を見つけてはならない”と書かれた『十戒』があり、これを破ると島に仕掛けられた爆弾が爆発するという状況下で、3日間の恐怖が始まる。」。犯人は『方舟』と同一人物? 孤島の密室ではなく島から逃れられない設定の中で、どうやって犯人を割り出していくかという筋立て、このままでは終わらないとは思ったがラスト数ページののどんでん返しはさすが! |
 |
銀河ホテルの居候 落葉松の森を歩いて
(ほしおさなえ)
図書館76
(904)78 |
シリーズ第3作(最新刊)、3編が収められている。「①50代の姉妹が幼い頃の記憶をたどり、手紙を書くなかで、家族へのわだかまりを少しずつ解いていく。②20代のホテル従業員の早乙女が亡くなった元オーナーの本『夜に想う』を書写することで、言葉を深く感じていく③毎年ゼミ合宿の引率にきていた斉藤教授は今年で定年に、巣立っていく学生たちに向けて最後のメッセージを綴る。」。このシリーズは、読んでいてとても心地よく落ち着く。今回軽井沢の旧市街などの描写が多く行ったことのない私にはすごく魅力的な街に感じたし、実際銀河ホテルがあったら泊まりたい、そこでインクが1000色ある手紙室に行ってみたいなぁと夢をみた。やはり、ネットより紙、本好きの人にはたまらないでしょう! |
 |
展望塔のラプンツェル
(宇佐美まこと)
図書館75
(903)
77 |
“ラプンツェル”とはグリム童話に出てくる少女の名前なのでホンワカした物語かと思いきや、貧困や家庭崩壊が蔓延る中、児童相談所の職員、街の片隅で暮らす貧しい男女、児童虐待から逃れてきた子どもたち。何と救いのない話と思いやめたくなるが最後までいった。「労働者の街として栄えた多摩川市が舞台(時代は1980年代半ば?)。児童相談所の職員・悠一が、虐待通報のあった家庭からいなくなった幼児を心配する一方、街で子どもを拾い『ハレ』と名付けて面倒を見るカイとナギサ。貧困や無法がはびこる中懸命にに生きいようとする彼ら…。」。児相の仕事の厳しさ、外国人差別、虐待。今の政治や、社会が現実に目を向けていないことがわかる、哀しすぎる!(時系列トリックに引っかかったが、これが救い)。 |
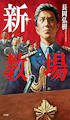 |
新・教場
(長岡弘樹)
図書館74
(902)
76 |
久しぶりに読んだ『隻眼風間公親の新シリーズ』、テレビではキムタクで何話も放映されているが原作はやはり面白い。今回は六つのお話。「『鋼のモデリング』:人命救助で表彰された生徒に、助教の尾凪が注目する。『約束の指』:マル暴刑事を希望している生徒。『殺意のデスマスク』:ブラジリアン柔術の有段者である若槻は、通り魔を逮捕した現場の再現を風間から命じられる。『隻眼の解剖医』:不快指数が高いと犯罪が起きやすいという日に課外授業の司法解剖が行われる。『冥い追跡』:成績トップクラスの星谷舞美と、同期の石黒とのストーカー問題。『カリギュラの犠牲』:卒業式のスライドの写真から、風間は最終講義を始める。」。実際にこんな教官がいたら怖いだろうな。でも、刑事としては最高! |
 |
人生、山あり“時々”谷あり
(田部井淳子)
75 |
映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の原案本(エッセイ)。「田部井淳子の生きる喜びに満ちた人生讃歌。“世界初”の称号と三度にわたる雪崩との遭遇、突然のがん告知と余命宣告、そして、被災地の高校生たちとの富士登山…。」。どんな時でも諦めず、最後まで山を愛した田部井さんの生き方がまぶしい。三度雪崩で死にかけた経験、山登りのお陰でポジティブに生きられることになったのかも?と、がんの告知を受けても、心静かに受け入れられたと。すごい人生観だが、理解ある優しいダンナさんに恵まれたことも幸せだったのだろうと思う、私なんかダンナさんの足元にも及ばないけど…。『身辺を片付けている暇なんかない。生きているうちに、自分のやりたいことをやった方がいい』。 |
 |
乱歩と千畝
(青柳碧人)
図書館73
(901)
74 |
直木賞候補。1935年の愛知五中の同窓会で、最前列に並んで座る乱歩と千畝の姿が写った記念写真を見て『もし二人が交流していたら』という発想から生まれた。「大学の先輩後輩、乱歩と千畝。まだ何者でもない青年、夢だけはあった。希望と不安を抱え、浅草の猥雑な路地を歩き語り合い、それぞれの道へ別れる…。若き横溝正史や巨頭松岡洋右と出会い、新しい歴史を作り、互いの人生が交差していく。」。若き日の作家たち(夢野久作、山田風太郎、二木悦子、松本清張など)の登場も興味深い。乱歩と千畝の波乱万丈の人生、何ともワクワクする物語で読後感がすごくいい。『年をとるとできないことが増える、できると思い直すができない。頑固さに嫌気がさす。人間最後には頑固さだけが残るのかもしれんな』。 |
 |
ダークネス
(桐野夏生)
図書館72
(900)
73 |
前作と合わせて1000ページを超えるが一気読み。「私の愛した男たちは皆行ってしまった。私の魂を受け止めてくれる相手はもうどこにもいない=『ダーク』から20年、60歳になった村野ミロは生きていた。そして息子のハルオは“悪”を知る旅に出るが…、息子を守るため、ミロの最後の闘いが始まる。」。このミロシリーズの第一作目は2000年に読んだ『顔に降りかかる雨』(著者のデビュー作)だったとは気が付かなかった。相変わらず先の読めない展開に翻弄されるが面白い、やはりこの著者は闇の世界を描くのが上手い。これが最後の戦いだとは思うが続編が読みたい、もしかすると息子のアキオを主人公に据えてさらなる世界が…。 |
 |
ダーク
(桐野夏生)
図書館71
(899)
72
|
新作『ダークネス』を読む前に、未読だった『ダーク』(2002年刊行)を読むことに。物語はすごい展開、500ページを超えるのに先が気にな読むスピードが速くなる。「出所を心待ちにしていた男が4年前に獄中自殺していた。何も知らされなかった村野ミロは探偵を辞め、事実を秘匿していた義父を殺しにいく。隣人のホモセクシャルの親友。義父の盲目の内妻。幼い頃から知っている老ヤクザ。周囲に災厄をまき散らすミロを誰もが命懸けで追い始める」。光州事件の詳細も描かれ、舞台は韓国にも飛んだり先の見えない展開に…。始めは登場人物になかなか感情移入できなかったが、話の面白さに引きずり込まれていった。23年前の主人公が20歳年をとり次回作になっているのが面白い、楽しみ。 |
 |
13月のカレンダー
(宇佐美まこと)
図書館70
(898)
71 |
“太平洋戦争終結から80年。愚かな戦争の記憶を継承する、至高の大河小説”と、読みたくなる。「疎遠だった父方の祖父母の家を相続した主人公・侑平が、15年ぶりに訪れた松山の家で、13月まであるカレンダーと祖母の闘病ノートを発見する。そこで侑平は祖父母のことを深く知らなかった自分に気づき、祖母の出身地・広島へと向かう。そこで原爆にまつわる祖父母の真実や、自身が知らなかったルーツを知ることになる。」。原爆投下後の悲惨さ、それに被爆者だけに留まらず、二世、三世と差別にさらされていく。核保有国や今の政治家はこんな現実をどう思うだろうか(政治家は読まないか)。『音楽を楽しむこと、将棋を指すこと、茶道を習うこと、それができる世の中であること。何気ない日常が平和なのだ。』。 |
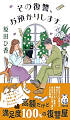 |
その復讐、お預かりします
(原田ひ香)
図書館69
(897)70 |
“読むほどに気持ちが晴れていく、自分の人生を取り戻すための物語”とあった。「腕利きの復讐屋・成海慶介の元を訪れた神戸美菜代。愛した男に騙された上に仕事を失ったので、その男に復讐してやりたいと。それには紹介状と高額の手付金と高額の報酬も必要とのこと。払えない美菜代は諦めきれず、成海の元で働くことに…。そこにはいろんな人が復讐を依頼してくる。」。
自分ではどうしようもない人生の不条理に直面したときどうする? 『復讐するは我にあり』(聖書の言葉)の意味を勘違いしていた“復讐は神に任せるべきであり、人間が自ら行うべきでない”と言うこと、まだまだ知らないことばかり。それに『人を呪わば穴ふたつ』、穏やかに生きましょう!2018年に出されたものの新装版、続編を出してほしい。 |
 |
銀河ホテルの居候
光り続ける灯台のように(ほしおさなえ)
図書館68
(896)69 |
シリーズ第2作。「銀河ホテルには、手紙室というすこし不思議な部屋がある。亡き妻が遺した謎のメッセージに導かれ、思い出の軽井沢を訪れた夫。趣味アカウントが炎上し、“好き”を奪われてしまったOL。人生の分岐点に立つ子を見守る母の願い…。やってきたお客さんは、手紙を書くことで自分の隠れた本音を見つめる。」。読んでいて優しさが胸に染みてくる。『私たち世代は、人の心を理解するのに文学が有効だと考えていた。文学で表現される人間の内面に自分たちの内面を重ねることができたからだ。だが息子や孫たちを見ていると、文学よりもAIやプログラムのようなものをモデルに人間をとらえているように見える』。ネットから切り離されたって人は生きていける、紙の本がいいなぁ…。 |
 |
架空犯
(東野圭吾)
図書館67
(895)
68 |
『白鳥とコウモリ』のシリーズ最新作だが、内容は前作とは関係ない。「焼け落ちた屋敷から見つかったのは、都議会議員と元女優夫婦の遺体だった。華やかな人生を送ってきた二人に何が起きたのか?
当初の無理心中説は、殺害方法の不自然さや犯人からの犯行声明などにより覆される。警視庁捜査一課の五代刑事と所轄刑事の山尾がコンビを組み、華やかな夫婦が隠し持っていた秘密に迫っていくが・・・。事件は関係者の40年前にさかのぼる。」著者は次から次に本を出しているが、どうしてこれだけの大量生産で内容を維持できるのか?いくらでも湧き出る泉のような頭の中を見てみたい。ミステリーとしては満足の出来、おすすめ! |

 |
踊りつかれて
(塩田武士)
図書館66
(894)
67 |
SNSなどネット上での誹謗中傷や週刊誌のでたらめ記事にいより、傷つき消えていった人がいかに多いことか、この本はこういった社会に警鐘を鳴らしている。「SNSでの誹謗中傷で死を選んだお笑い芸人・天童ショージと、週刊誌のデタラメ記事で姿を消した伝説の歌姫・奥田美月。ある日突然、『枯葉』と名乗る人物がブログに【宣戦布告】し、天童と美月を傷つけた人々の個人情報を次々と暴露し始める。この行為が引き起こす報復の連鎖と、芸能界の裏側、そして現代社会における“正しさ”と“正義”の危うさ…」。読み応えがり、今自分の思っていることばかりで納得!『SNSはそれが世直しであれ糾弾であれ、悪意と嘘が蔓延する砂漠』『ネットの質感のなさや手軽さが、責任感や罪悪感を消し去ってしまった』『ネットのインフラ化によって“瞬時に答えがわかり好きなものだけを手に入れられる”、その結果“事実より面白いことを優先する”“自分が信じたい情報ばかり集める”“承認欲求を満たすため感情を吐き出す”人たちが増えた』『“醜い言葉の刃で誰かを追い詰めること”“感情に任せて私刑を誘発すること”“嘘の情報をタレ流すこと”“正確さよりも面白さを優先すること”がいつから認められるようになったのか?』など、私はネットの匿名性に問題があると思う、やはり規制は必要。安心できるネット世界であって欲しい。 |
 |
紅色の幻
(あさのあつこ)
図書館65
(893)
66 |
おいち不思議がたり最新刊(第7弾)。「夫・新吉が帰ってこない―。不安に駆られたおいちだったが、新吉は朝になって、何事もなかったかのように家に戻ってきた。しかし、新吉が言付けを頼んだ職人らしき人物が、菖蒲長屋近くで殺されていたことが判明する。しかもその懐には、きれいなビードロの風鈴がしのばせてかあった。おいちは、身重であることも忘れ、岡っ引の仙五朗とともに、事件の解明に乗り出す。そんな折、おいちは石渡塾で共に学ぶ和江が、血飛沫を浴びたかのように紅く染まった幻を見てしまう。」。相変わらずテンポのいい展開、面白く読みやすいのであっと言う間に読んでしまう。ラストでついに出産を迎えるが男の子かな、女の子かな?今、TV で放映中。 |
 |
BUTTER
(柚木麻子)
図書館64
(892)
65 |
2025年の英ダガー賞最終候補作品に選ばれている(受賞は王谷晶の『ババヤガの夜』)、刊行されたのは2017年。2009年に発覚した『首都圏連続不審死事件』の被告・木嶋佳苗をモデルにしている。「梶井真奈子は、中高年男性に金を貢がせたうえ、殺害した容疑で逮捕された。一方、週刊誌記者の町田里佳は何とか面会を取り付け独占記事を執筆を試みる。塀の中にいて望みのものが口にできない梶井は里佳にテストめいた要求を出す。梶井が指定する食べ物、食べ方を里佳が体験し、梶井に伝えるのだ。その日以来、欲望に忠実な梶井の言動に触れるたび、里佳の内面も外見も変貌し、人の運命をも変えてゆく。」かなり濃厚な内容、読み進めるのに時間がかかった。調理のシーンが多いのは参った。 |
 |
夫婦じまい
えにし屋春秋
(あさのあつこ)
図書館63
(891) 64 |
女着物に身を包んだ〈えにし屋〉お初シリーズ第3作。「えにし屋は人の縁を扱うことを生業とする。今回は一度嫁いだが離縁して戻ってきた娘に再度縁を結んで欲しいと大店の主から依頼される。簡単に片付くと思えた依頼だが、娘のお藍は何かに怯えているようで塞ぎ込み、離縁の理由も分からず、どんどん複雑になっていく。過去の犯罪とそれに起因する怨恨が招いたものでその事件は酷かった。」。親子・夫婦の情愛・怨恨など複雑に窯見合って面白かった。今、TVで『おいち不思議がたり』が放映中、他に『弥勒シリーズ』『闇医者おゑんシリーズ』などたくさんあるが、どのシリーズも面白い。よくこんなにいろんな話が書けるものと感心する。 |
 |
ポピュリズム
(堂場瞬一)
図書館62
(890)
65 |
「20××年、10数年前から日本に取り入れられた直接民主制。国会は廃止され、議員は20歳以上の国民からランダムに選ばれる。首相選に立候補するための条件は、『日本国籍を持つ30歳以上の人』で、供託金は1億円。投票するのは、全有権者。立候補が見込まれるのは、女性首相を目指す新日本党の政治家、関西を中心に絶大な人気を誇るTVタレント教授、SNS総フォロワー数800万人以上のインフルエンサーなど…。」。どうにもならない政治家、そして国民を描いた近未来?小説。現実に今の政治にうんざりしている人たちは、こんな社会を夢見るのかも?現実からは遠く離れているが、ちょうど自民党総裁選の直前、総理大臣が代わるタイミングで読めたことでより興味がわいた。 |
 |
たびじ
(浅田次郎ほか)
図書館61
(889)
64 |
旅をテーマに7人の作家によるアンソロジー。「浅田次郎:椿寺まで、池波正太郎:かたきうち、梶よう子:長崎奉行、西條奈加:氷目付、佐江衆一::峠の伊之吉、澤田瞳子:忠助の銭、澤見彰::高尾参り」。さすが時代小説の名手たち、全てに読みごたえがあった。私は、飛行機やバスの中で読んだが、まあこの時代の人はよく歩くもんだ、駕籠しかない時代だから歩くしかないんだけど、この足腰の丈夫さはホントに尊敬。浅田ファンとしては“椿寺まで”がよかった、これぞ胸アツ浅田節。それと、最後の高尾山参りは空想まじりの落語的なお犬さまの物語で笑わせた、また高尾山に登りたくなった。旅のお供にはもってこいの本でした。 |
 |
銀河ホテルの居候
また虹がかかる日に(ほしおさなえ)
図書館60
(888)63 |
「南軽井沢の銀河ホテル。イギリス風の瀟洒な洋館の一角に、世界中のインクを取り揃えた『手紙室』がある。室長の苅部文彦は、このホテルに居候する風変わりな男。彼の手紙ワークショップを受けると、なぜか心の奥のほんとうの気持ちが見えてくる。」。初読み作家、気持ちがホンワカしてくる、何か特別なことがなくてもいいのだと。“山歩きとは不思議なもので、苦しかったことは全部忘れ、上りきった爽快感や途中のきれいな風景など、いい記憶だけが残っている。
しんどいときもあって、自分ではすごくがんばってきたつおyおやこもりなのに、いつの間にか頭のなかで濾過されて、楽しかった記憶だけが残る。”と、こんなこと誰にもあるよね。『本は、人の知恵や心を遠くに送り届けるためのものでしょう』。 |

 |
楽園の瑕
(相場英雄)
図書館59
(887)
62 |
『震える牛』『ガラパゴス』に連なる『覇王の轍』に次ぐ樫山順子シリーズの第二作。社会派ミステリー、最高に面白かった。小泉改革、竹中平蔵を彷彿させる郵政改革、派遣の規制緩和の名のもと日本経済を壊し格差社会を作った男…、郵政民営化で日本が壊れ始めたときから現代(熊本の半導体工場)まで地方創生にかかわる陰謀、利権がどのように動いていたか?「北海道警から山梨県警に異動した樫山順子は、大規模農場開発に怪しい動きを嗅ぎつけた。地元政治家らの間で暗躍するのは、かつて規制緩和の名たのもと経済を壊した男。中国の強欲投資家も加わった資本主義の魔手から、樫山はかつての伝説の金融コンサル・古賀と手を組みながら挑んでいく。山岳の楽園を守れるか?」。
・教育や福祉など本来なら公的部門が担うべき業務においても“竹中”が標榜した新自由主義が暴走した結果、日本は深刻な格差社会に陥った。 ・公的サービスを担う郵便事業、貯金事業など、すべて民営化の対象となった結果、不採算部門のサービスが低下し、料金も年々上がっています。それに社員たちが過度なノルマを課せられ、違法なセールス活動で保険が売られたこともあった。また、かんぽの宿の異常な安値での売却など…。 ・今後の国家戦略の中で、半導体関連の誘致は最優先のプロジェクトです。九州や北海道では建設に漕ぎ着けるまでの間、土地の買占めが起きトラブルが発生。・台湾の大手半導体企業が進出した熊本では求人が増えたことで人件費も跳ね上がった。割を食った地元の個人商店が、急上昇してしまった高額時給に耐えられずに閉店するなどの事象が起きている。 ・“竹中”の強引かつ独善的なやり方、そして露骨な利益誘導体質を批判する声が上がっていたが、世間は穏やかな経済学者としてみなしてきた。彼の本当の顔は日本を裏から操ってきたフィクサー(陰でよからぬことを企む人、黒幕)です。 |
 |
逃亡者は北へ向かう
(柚月裕子)
図書館58
(886)
61 |
『孤狼の血』『盤上の向日葵』の著者が地元・東北を舞台に描く震災クライムサスペンス。「大震災直後に殺人を犯し、死刑を覚悟しながらもある人物を探すため姿を消した青年。自らの家族も被災した一人の刑事が、執念の捜査で容疑者に迫る。壊れた道、選べなかった人生…、被災地で繰り広げられる逃亡劇!」。どこか一つでもきちんと歯車が合えばよかったのに。いろんなつらいことがあっても、一生懸命生きようとしていたのに。歯車が一つ狂っただけでたどる人生、切ない。一気読みだが読むのかがやりきれない結末、苦しかった。あの大震災の中で、家族を失ったものの悲しみがひしひしと伝わってくる。家族を失った者、みんな無事だった者、誰もがが苦しんだ。立ち直って幸せになってほしい。 |
 |
おぼろ迷宮
(月村了衛)
図書館57
(885)
60 |
月村了衛と言えばアクションや社会派サスペンス。しかし、今回はシリアスなものではなくエログロもなく、ほっこりするお話、安心して読める。4話から構成されている。「おんぼろアパート“朧荘”に住む女子大生夏芽は、いくつかの不可解な出来事に遭遇する。〈謎〉を解決するのは、隣に住む正体不明の老人、鳴滝。尋常ならざる人脈と驚異の推理力を駆使する彼は一体何者なのか。街にはびこる不可思議な事件の謎を、凸凹コンビが華麗に解決!」。メインは第3話だけど、警察署内の4000万円盗難事件。冤罪事件かと思えが裏金事件。ちょっとあっさりしすぎではあるがそれなりに面白い。笑える部分も多くクスっとしながら読んだ。熊日ほか新聞に連載されていたもの。 |
 |
暦のしずく
(沢木耕太郎)
図書館56
(884)
59 |
沢木耕太郎、初の時代小説。江戸時代中期の宝暦8年に獄門(死刑)に処せられた実在の講釈師、馬場文耕を主人公に描く物語。「長屋に住む文耕が、なぜかつて武士の身分を捨てて刀を捨て、講釈師なり、そして死刑に至ったのか、その謎に満ちた生涯」。ほとんど資料の残っていない文耕の生涯を爽やかに描いている。500ページを超えるが一気読み。国家とジャーナリストの関係についても考えさせられる。『額に汗をして銭を稼いだこともなくただ年貢米や俸禄米を手にするだけの御方ひには、巷に生きる者の苦しさなどわかりますまい。だから、政(まつりごと)が民を助ける正しいものになっていこうとしないのです』。朝日新聞日曜版に2年近くにわたり掲載されていたもの。 |
 |
天網
TOKAGE2
(今野敏)
図書館55
(883)
58 |
続けて読んだ、シリーズ第2弾。今度はネットが絡んだ犯罪、15年以上前にこんな話を考えつくなんて…。「新宿発名古屋行きの高速バスがバスジャックされた。続けてもう2件、なんと同時に3台のバスジャック事件が発生。犯人からの要求はなく、3台のバスは首都高を周回しているという。一体犯人の目的とは?バスをバイクで追うトカゲ、それにSIT、SATの投入…。」。今はこれ以上にネットを悪用した事件が起きている気がする。『新聞が売れなくなっているのは、新聞でわかるようなことは、ネットでわかってしまうからです。端末を持ち歩けばいつでもどこでもニュースを手にすることができるから』。『「ネットの世界ってのは腐ってるな」
「そうですか?現実社会の縮図だと思いますけどね』。 |
 |
TOKAGE
特殊遊撃捜査隊
(今野敏)
図書館54
(882)
57
|
約20年前に書かれたものだが、今回TVドラマ化されるとことで読んだ。これが結構面白かった。「大手都市銀行の行員3人がさらわれる誘拐事件が発生した。身代金要求額は10億円。警視庁捜査一課特殊犯係の白石涼子と上野数馬は、覆面捜査専門のバイク部隊『トカゲ』のメンバーとして、東京・大阪間を駆け巡り、初めての誘拐犯逮捕に挑むが…。」。『トカゲ』とは、警視庁の捜査1課の特殊捜査隊SIT。そこに所属しバイク特有の機動力を駆使して追跡などを行う警察官のこと、ホントにいるのかな?背景にはバブル後の銀行の貸し渋りなど“銀行は諸悪の根源”みたいなところもあり、何となく納得されられた。銀行にいい印象を持っていない人にはお薦め! |

 |
トットちゃんとカマタ先生のずっとやくそく
(黒柳徹子
鎌田實)
図書館53
(881)
56
|
徹子さんとカマタ先生の対談集。「『約束』というテーマを通じて、信頼や絆の大切さを描いたお話。トットちゃんと、心優しく頼れるカマタ先生との間で交わされる約束は、どんなに小さなものであっても人の心を支え、人生に彩りを与える力を持つことを教えてくれる。」。と。LD、先生大好き。ボタンが苦手、殖民地になっていない幸福についての文章、難民キャンプで男の子
おっぱい掴まれた話など…。『みんな一緒だよ』と言う考え方。ひとつひとつが考えさせらることばかり、20年近く前の本だが今の世の中確実にこのころより悪くなっている。
・子供っておとなを信じてる、だから私たちおとなは子供を裏切ってはいけない。
・人と比べない「あの人はどうしてあんなにきれいなんだろう」「あんなにお金持ちなのか」と思ってもその人になれるわけはない。それよりも、どうしたら自分もそうなれるかなと考えた方がいいでしょう?
・人間を政治の違いや宗教の違い、国の違いで見てはいけない。
・「命は大事なもの」ということを赤ちゃんの時から知らせていかないとコンピューターを再起動させるように、ゲームをやり直すように子供たちが命をとらえているなんて、そう思い込むような社会を私たちおとなが作ってしまった。
・日本だって戦争こそないけれど、ぎすぎすしているのは同じ。ぎすぎすしているからグチを言ったり恨んだりしやすい。
・豊かならもっと幸せであっていいのにそう感じていない人が多いのは、経済優先、お金優先の社会を作ってきたツケが現れている。
・次々と何かをしたいと気持ちでいられる人は、いくつになってもたとえ身体が動かなくても「老人」とは呼ばなくていい。
・「平和」だからできることはたくさんある。この国が好き。この国を戦争をする国にはしたくない。 |

 |
東京輪舞(ロンド)
(月村了衛)
図書館52
(880)
55 |
昭和・平成の日本裏面史を『貫通』する公安警察小説!「かつて田中角栄邸を警備していた警察官・砂田修作は、公安へと異動し、時代を賑わす数々の事件と関わっていくことになる。ロッキード、東芝COCOM違反、ソ連崩壊、地下鉄サリン、長官狙撃、金正男…。」イヤァ~、最高に面白かった。歴史の闇に隠れた部分、考えるだけでぞっとする。常に事件の背後にはCIA,KGB、中国それに北朝鮮と、今の時代はまだひどいのだろうな。私たち国民はほとんど、事件の中身がわからないままに時が過ぎていくことがよくわかる。『ロッキード事件は田中角栄という生意気で目障りな日本人を排除するためにキッシンジャーが仕掛けた罠だったのではないか』
『小泉は構造改革の構造とは、角栄が作った政治構造のことであると語っていた。そうしたものを一切否定し、一点突破を図るというのが郵政民営化であるというのだ』
『ヘイトを主張するトランプ政権が誕生した。常にアメリカに追従する日本でも、あからさまに差別を煽る輩が跋扈している。〈戦争を知る世代が社会の中核にある間はいいが、戦争を知らない世代ばかりになると怖いことになる〉と角栄の言ったとおりになった』。 公安刑事の主人公とロシア美人スパイの話がちょいと切ない。 |
 |
夜刑事
(大沢在昌)
図書館51
(879)
54 |
ウイルス感染させられて夜にしか活動できなくなった刑事の活躍。「ヴァンパイアウイルスと呼ばれる未知のウイルスに感染し、夜しか活動できなくなった刑事の岬田は、その代り、極端に研ぎ澄まされた五感を手に入れた。彼は、ウイルスに感染した犯罪者たち、そして感染者を排除しようとする活動家たちの思惑に巻き込まれながらも特命任務にあたり、ウイルスを感染させた元恋人の明林を捜そうとする…」。ちょいと異色の刑事もの、あり得ない話だが面白い。最近の犯罪ものには中国人、ベトナム人などが絡むものいsが多いが、実際に技能実習生として来日したもののあまりにもひどい待遇に犯罪に巻き込まれていく様はわかる。政治や社会の仕組み、あとからこんなことになってしまう愚かさ。 |
 |
小さいわたし
(益田ミリ)
図書館50
(878)
53 |
気持ちがやさしくなる本 “おとなになると今日のことを忘れてしまうのかな。そうだとしたら、すごくいやだ。こどもの頃のわたしは、いつもそんなふうに思っていたんです”と、益田ミリが小さい頃に書いていた日記を元にした38点の描き下ろし。カラーイラストも掲載
「小学校1年生の女の子の日記、胸に抱いた繊細な気持ちを、丁寧に、みずみずしくつづります。『入学式に行きたくない』『線香花火』『キンモクセイ』『サンタさんの家』など、四季を感じるエピソードも収録。かけがえのない一瞬を切り取った、宝物のような春夏秋冬。」。こんなに沢山のエピソードを自分は覚えていないが、著者はきっと素敵な女の子だったんだろうな。『こども時代は本当に短いものです。長い人生の本のひととき。』。 |
 |
香港警察東京分室
(月村了衛)
図書館49
(877)
52 |
2冊続けて月村良衛、“ニッポンに香港・北京の公権力が密かに棲みついてしまった…。西側のインテリジェンス・コミュニティはそう疑っている”かも知れないと思われるお話。「警視庁と香港警察との間で捜査協力を目的として新設された国際犯罪対策課特殊共助係には、日本・香港の警察官が各5人づつ所属。香港で2021年に起こったデモを先導した大学教授キャサリンの捜査・確保に向けて動くが、潜伏先で中国の犯罪グループらの妨害に遭う…。」。捜査員同士も何を考えているかわからない、アクション、頭脳戦、心理戦。手に汗握る面白さ。『あなた達は権力に対して従順であるばかりか、抵抗する人、疑問を投げかける人を嘲る。日本は香港よりもたやすく独裁主義,全体主義の手に落ちるでしょう』。 |
 |
虚の伽藍
(月村了衛)
図書館48
(876)
51
|
直木賞は逃したものの『高校生直木賞』(直近1年間の直木賞候補作の中から“今年の一冊”を高校生が選ぶもの)を受賞。「日本仏教の最大宗派・燈念寺派で弱者の救済を志す若き僧侶・志方凌玄。バブル期の京都を支配していたのは、暴力団、フィクサー、財界重鎮に市役所職員…古都の金脈に群がる魑魅魍魎だった。腐敗した燈念寺派を正道に戻すため、あえて悪に身を投じる凌玄だが、金にまみれた求道の果てに待っていたのは…」。京都弁は、優しい雰囲気があるのに、ヤクザ映画を見ているような迫力ある恐ろしい話だった。人を救うための仏教の内部は金と権力に明け暮れている。京都の闇、これも実際と近いものがあるのだろうか?。人間、どうしても金と権力には弱い。 |
 |
渦の中へ
(あさのあつこ)
図書館47
(875)
50 |
“おいち不思議がたり”第6弾、おいちついに結婚。「おいちと新吉の祝言の日に事件が起きる。大店で食あたりが起こり、医者としては祝言どころでない。原因は毒物が混入されていた?数日後、店の乳母が自白の遺書を残して自死。以前長屋に居た男の不可思議な行動と今回の事件は関係があるのか。岡っ引きの親分とともに真相を探り始める。そんな中、おいちのお腹には赤ん坊が…」。女医を志す女性たちの心意気、おいちに訪れる大きな変化。親分・仙五朗と叔母のおうたがカッコよくて面白い!女性蔑視の時代、女性が医師になることの難しさ塾生も増え前に進んでいく彼女たちの逞しさが今後楽しみ。また、おいちは医者の仕事と母親として家庭を両立できるのか?ますます目が離せなくなる。 |
 |
女の国会
(新川帆立)
図書館46
(874)
49 |
タイトルから少し軽いものを想像していたが、さすが山本周て五郎賞受賞。読み応えがあった。政治大逆転ミステリー!「野党第一党の高月馨は窮地に追い込まれた。敵対関係にありつつも、ある法案については共闘関係にあった与党議員・朝沼侑子が自殺したのだ。死の前日の浅沼への叱責が彼女を追い詰めたのではないかと批判が集まり、謝罪と国対副委員長の辞任を迫られてしまう。だが、長年ライバル関係を築いてきた高月には朝沼の死がどうも解せない。」。代議士、市会議員、政策担当秘書、新聞記者として活動する女性の覚悟が少しづつでも世の中を変えていけるか?どうしようもない腐った爺さんたち政治家、これぽっちも国民のことは考えていない。現実社会を見ているよう。爽やかな読後感。 |
 |
伊豆の踊子
(川端康成)
48 |
『伊豆の踊子』他に三篇『温泉宿、抒情歌、禽獣』を収録。来年“踊子歩道”を歩きたいと思っているので出何十年かぶりに読んでみた。内容は皆さんご存じでしょう「旧制高校の私は、一人で伊豆を旅していた。途中、旅芸人の一行をみかけ、美しい踊子から目が離せなくなる。彼女と親しくなりたいが声をかけられない・・、そんな時向こうから声をかけられ忘れられない旅が始まる。」。映画化6回(田中絹代、美空ひばり、鰐淵春子、吉永小百合、内藤洋子、山口百恵)、まさに“青春の文学”爽やかな涙。他の『温泉宿』は昭和2年、宿の女中と酌婦たちの流転を描いた哀しい女たちの話。『抒情歌』と『禽獣』は解説を読まないと私には理解しかねた。『伊豆の踊子』はほのかな旅情と青春の哀歓を描いた傑作!その通り。 |
 |
いけないII
(道尾秀介)
図書館45
(873)
47 |
いやぁ~、さらに衝撃アップ!最終章の写真以外は全然わからなかった。「第一章“明神の滝に祈ってはいけない”行方不明になった姉を探す妹がたどり着いた『願いを叶える滝』その代償とは。第二章“首なし男を助けてはいけない”夏祭りの日、親に内緒で肝試しを計画する少年たちは引きこもりの伯父さんから奇妙な『首吊り人形』を借りる。第三章”その映像を調べてはいけない”前の晩に息子を殺したと自白する年老いた容疑者。しかし遺体は見つからず、捜査は暗礁に乗り上げる。終章“祈りの声を繋いではいけない”前作を超える、驚愕のラスト!」。やっぱりイヤミス、話は結構ダークなので、明るく楽しい話が読みたい!という方には向いていない。謎解きが好きな方には面白いと思う。 |
 |
いけない
(道尾秀介)
図書館44
(872)
46 |
小説を超えた体験型ミステリー!まさに自分がその場にいるような怖さあがある。四つの章からなるが終章を読み終えるとなると騙されていたことに気づく。「第1章“弓投げの崖を見てはいけない”自殺の名所付近のトンネルで起きた交通事故が、殺人の連鎖を招く。第2章“その話を聞かせてはいけない”友達のいない少年が目撃した殺人現場は本物か?
偽物か?第3章“絵の謎に気づいてはいけない”宗教団体の幹部女性が死体で発見された。先輩刑事は後輩を導き捜査を進めるが。そして最終章“街の平和を信じてはいけない”と続く」。各章の終わりの写真が真相を表している…、わからなかった。再読すると物語に隠された〝本当の真相〟が浮かび上がるだろうと思える。Ⅱでは騙されないよう…。 |
 |
星に祈る
(あさのあつこ)
図書館43
(871)
45 |
シリーズ第5弾、おいち20 歳。「深川で立て続けに、謎の行方不明事件が起きる。忽然と姿を消した四人に、共通点は何一つ見つからない。そんな時おいちの許に、岡っ引の仙五朗が思いがけない情報を携えてやって来る。この世に思いを残して死んだ人の姿を見ることができるおいちは、仙五朗と力を合わせ、事件を解決に導くことができるのか?一方、心を寄せ合う新吉との関係も、新たな局面を迎えることに。」。真相は陰惨。女性差別・終末医療など現代にもある問題ばかり・・・。しかし、おいちはやっと医術を学ぶ機会を得た、そして新吉との未来が見えてきた。またまた先が気になる、早く続きが読みたいが終わってほしくない気もする。とても好きなシリーズ! |
 |
火花散る
(あさのあつこ)
図書館42
(870)
44 |
シリーズ第4弾、おいち19 歳。「菖蒲長屋で赤子を産み落とし、消えた女。おいちは、その女の聞こえるはずのない叫びを聞いてしまう。岡っ引・仙五朗らと力をあわせ、女を捜していたおいちのもとに、女が惨殺され、無残な姿で見つかったとの報せが…。傷痕から見えてきた女の正体、女が抱えていた事情、そして母を亡くした赤子の運命は?」。武家社会の韻部を絡ませて物語は進む、命を捨ててでも子供を守るという母の強さに心打たれる。TVドラマを見ていないのが残念。現在シリーズは7弾まででている。『幸せってものは誰かにわけてもらうもんでも、譲り受けるもんでもないだろう。己が手で入れるものだ。人が幸せになれるかどうかはその者がどう生きるかにかかっている。 |
 |
月とアマリリス
(町田そのこ)
図書館41
(869)
43 |
『52ヘルツのクジラたち』の著者が描くサスペンス、だがただのサスペンスではない。濃すぎる内容だった。「報道記者をやめて北九州でフリーペーパーの記事を書く仕事をするみちる。かつての恋人からの電話で地元で白骨死体が見つかったことを知る。調査していく中で若い女性の死体を発見する。
連続殺人として捜査されることになった事件の犯人と目されたのはみちるの同級生だった…。」。声なき声を届けたい、みちるの叫び!報道の在り方、ジェンダーや家庭問題それにいじめなど現代の様々な問題をこれでもかと突き付けられる。『無意識に誰かを傷つけて、でも傷つけられたことだけをしっかりと覚えて、自分だけはまっすぐに生きてきたような顔をしていた自分自身が怖い』。 |
 |
春立つ風
(あさのあつこ)
図書館40
(868)
42 |
『弥勒シリーズ』最新作(第13弾)。「油屋の長男が刃物で喉を突いて離れで自死をする。外から開けられない状況で奉公人が打ち破って入り若旦那の遺体と遺書を発見。放蕩息子と評判だったが、番頭と女中の若旦那の評価には若干の違いがある。後添えが生んだ年の離れた弟の存在、若旦那の馴染みの女郎の証言などから自死に疑いを感じ始める伊佐治。一方、相変わらず掴みどころのない不穏な空気感の小暮信治郎だが心眼に狂いはない。」。今回は、さほど大きな動きは無い内容、恐らく次の作品で大きく動き出すのでは、何となく予感がする。やっぱり面白い!『あっしたちみてえな巷を這いずって生きている者は、憐れんだり労わったり助け合ったりしねえと、生きていけやせんからね』。 |


 |
疾走する刻 (冒険の森へ 傑作小説大全20)
次の2人のほか7人の作家
「川の深さは」
(福井晴敏)
「スナーク狩り」
(宮部みゆき)
図書館39
(867)
39~41 |
『冒険の森へ 傑作小説大全20』(2015年発行)には5編のショートストーリー、2編の短編と2編の長編が収録されている。ショートストーリーには船戸与一、景山民夫、眉村卓、中島らも、北方健三。中編は海音寺潮五郎と佐々木譲そして長編は福井晴敏と宮部みゆきの二人。ページ数も2段組みで600ページを超えるので3冊分くらいの分量がある(と言うことで3冊に換算)。
・ショートストーリーも全てが面白い。中編の海音寺潮五郎は「男一代の記」:戦国時代から江戸初期にかけて薩摩に実在した中馬大蔵重方の評伝、“ぼっけもん”の代表。それと、佐々木譲の「鉄騎兵、跳んだ」:モトクロスレースに挑む若者の勇姿を描いた青春小説の傑作(著者のデビュー作)
『川の深さは』(福井晴敏):世界を敵に回して、少女を守りぬこうとする少年。その姿にかつての自分を感じた元刑事の警備員は、彼を匿うことにした。そして、物語は『地下鉄テロ』の真実へと向う…。「阪神淡路大震災があり、教団が地下鉄を爆破、警察庁長官は暴漢の襲撃に遭い世の中は未曾有の混乱に陥る。桃山は警視庁マル暴の警部補だったが組織に嫌気を差して警備員に。そこにヤクザに追われ怪我をした青年保と凛とした少女葵が逃げ込み匿うことに。公調、警察、自衛隊、教団、政界がからんでくる」。著者の処女作。
『スナーク狩り』(宮部みゆき):1992年に刊行されていて、まだ携帯電話も無い時代の話、だから?すごく面白い。「関沼慶子は散弾銃を抱え、かつて恋人だった男の披露宴会場に向かっていた。すべてを終わらせるために。一方、釣具店勤務の織口邦男は、客の慶子が銃を持っていることを知り、ある計画を思いついていた。今晩じゅうに銃を奪い、“人に言えぬ目的”を果たすために。いくつもの運命が一夜の高速道路を疾走する。人間の本性を抉るノンストップ・サスペンス。」。手に汗握るロードムービーそのもの。 |
 |
あなただけの物語のために
(あさのあつこ)
図書館38
(864)
38 |
作家・あさのあつこが若き日を振り返り、生きがたい日々を送る中高生に向けて届けるメッセージ!「世の中には紛い物の物語があふれており、うっかりすると飲み込まれてしまいそうになります。しかし、その物語はあなたの物語ではありません。書いたり、読んだりを通して、自分の内にあるあなただけの物語を見つめてみましょう。」。中高生に向けて書くことの面白さを伝えているが、読んでいてこちらまで若くなっていく気がする。SNSだけじゃないよと言いたい。『喜びでも悲しみでも怒りでも、s渦中にいるときは見えないものがたくさんあります。渦の真ん中にいては、渦全部を俯瞰できませんからね』
。 |
 |
青い壺
(有吉佐和子)
図書館37
(863)
37 |
1984年53歳で亡くなった著者の約50年前の作品、何という面白さ!ひとつの美しい壺めぐる十三の連作短編集。「無名の作家が生み出した青磁の壺。売られ盗まれ、十余年後に再会するまでに壺が映し出した数々の人生。定年退職後の虚無を味わう夫婦、戦前の上流社会を懐かしむ老婆、45年ぶりにスペインに帰郷する修道女、観察眼に自信を持つ美術評論家・・・」
人間の奥深くに巣食うドロドロした心理を小気味よく、鮮やかに描き出している。『親父もおふくろもわがまま同士で、喧嘩ばかりしていた。おふくろが親父を褒めるようになったのは親父が死んでからだ。・・・片方が死ねば愛は完結するのかと思った」。原田ひ香が“こんな小説を書くのが私の夢です”と言っている。 |
 |
老人ホテル
(原田ひ香)
図書館36
(862)
36 |
タイトルから様々な老人かホテル暮らしをする話と思ったがそれだけでなく、そこの清掃員の仕事をやってしている若い女性の話。「生活保護で暮らしている大家族の中で、高校を中退して無気力にキャバ嬢をしていた天使(えんじぇる)は孤独な老人たちが長期滞在するホテルに就職。そこに住む光子に、生きる術を教えてほしいと願い出る…。生き方や蓄財のノウハウを伝授され、天使の生活は少しずつ変わり始めるが、やがて世代が違うふたりの過去と秘密が明らかになる。」。生保だけで全く仕事をしな毒親、主人公の悲惨な育ちが哀しい。この著者の本を読と最後はお金なぁってことになる。『あんたっていろんなことを始める前に諦めてるよね。どうせダメだからて。だけど本当のところあまりやったことなんてないんだろ』。 |
 |
リペアラー
(大沢在昌)
図書館35
(861)
35 |
“リペアラー”とは修復者、この本では歴史の修復の意味を持っている。「ノンフィクション作家の穴川雅は40年前の六本木のビル屋上の行旅死亡人についての調査依頼を受け、友人の想一と共に着手。依頼人は不明。2人は王道の警察・探偵小説の如く地道に関係者を当たって行く。やがて諜報機関の暗躍・国家機密などが絡んでくる…」。後半はどうなるのかと思ったけれど最後はこう来たかという感じ、あっさりとし過ぎていてちょっと残念。でも(大沢在昌にしては軽すぎる感じもするが)面白かった。因みに“行旅死亡人”とは身元不明の引き取り手のない遺体のこと。『警官も軍人も体制を守る暴力装置だから、体制と法、どちらを優先するかで、その国の程度が知れる」。 |
 |
闇に咲く
(あさのあつこ)
図書館34
(860)
34 |
シリーズ第3弾。おいち18歳、今回はちょいと血なまぐさい。「町医者、松庵とおいちのもとに、血の臭いを漂わせた男がやってくる。商家の若旦那だというその男は、亡き姉の影に怯え、おいちに救いを求めてきたのだ。一方、おいちの住む深川界隈では、夜鷹殺しが立て続けに起きていた。腹を一文字に裂くという猟奇的な方法に衝撃を受けたおいちは、岡っ引・仙五朗と力をあわせ、絡み合った因縁の糸を解きほぐしていく」。終盤、一件落着かと思いきや思いがけない伏線が仕込んであった。やはり一筋縄ではいかない面白さ。春を売る女性の哀しさ、人間の哀しさが身に染みる。一番恐ろしいのは人の心! |
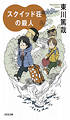 |
スクイッド荘の殺人
(東川篤哉)
図書館33
(859)
33 |
『謎解きはディナーのあとで』の著者の作品。ドタバタ群像劇としてなら好きな人は楽しめるのかなと思うが、あまりにも軽すぎて私には合わなかった。「閑古鳥さえ寄りつかない鵜飼探偵事務所に、待望の依頼人が訪れた。その男は、なんと烏賊川市の有力企業社長・小峰三郎。彼は、クリスマスに宿泊するスクイッド荘に同行し、脅迫者から自分を護ってほしいという。断崖絶壁に建つ奇妙な形のスクイッド荘は大雪に見舞われ、いかにも怪事件が起こりそうなムード。探偵と助手が酒と温泉にうつつを抜かしている間に、殺人者はひたひたと忍び寄る」。20年前のバラバラ事件も絡み話は面白いのだけど、無駄な会話が多くて疲れた。 |
 |
桜舞う
(あさのあつこ)
図書館32
(858)
32 |
シリーズ第2弾。「医者である父・松庵の仕事を手伝うおいちは17歳。父のような医者になりたいと夢を膨らませているのだが、そんなおいちの身にふりかかるのは、友の死、身内の病、そして自分の出生の秘密にかかわる事件等々。おいちは、様々な困難を乗り越え、亡き友の無念を晴らすことができるのか…。」。今回、新しい人物が登場、それは
『おふねを亡くして悲しむおいちともう一人の親友おまつ。野蛮な男達に絡まれたところを助けてくれた医師を目指しているいう若き医者・田澄』、このあたりからおいちの出生に隠された秘密が明らかにってくる。まるでドラマを見ているように登場人物がイキイキと動き出す、TVドラマになるはず見逃して残念。先が気になりやっぱり一気読み。 |
 |
80歳でも脳が老化しない人がやっていること
(西剛志)
図書館31
(857)31 |
脳科学者・西剛志の本。なるほどとは思ったが、想像した内容だった。脳を老化させないためには『怒らない、イライラしない、ストレスをためない、頑固にならない(自分の考えにとらわれない、自分が正しいとは思わない・・)』など、反省させられることは多かった。脳にとっての3大NG
ワード“老けた”“歳をとった”“もう若くない”、それに“わからない”難しい”も使わない方がいい、など。逆に、これはいいと思ったのに『パソコンに趣味があると認知症になりにくい(写真を整理することなど認知機能を高める)』と。最後に老人脳には5つの「老化が起きやすい部位」がある、①「やる気脳」②「記憶脳」③「客観・抑制脳」④「共感脳」⑤「聴覚脳」、どれが自分に当てはまるか?くよくよせずに前を向いて生きましょう! |
 |
おいち
不思議がたり
(あさのあつこ)
図書館30
(856)
30 |
シリーズもので現在第6巻まで出ている、これは第1巻で2011年に刊行されている。「おいちは16歳。江戸深川の菖蒲長屋で、医師である父の仕事を手伝っている。おいちが他の娘と違うのは、この世に思いを残して死んだ人の姿が見えること。そんなおいちの夢に、必死で助けを求める女が現れる。悩みながらも己の力で人生を切り拓き、医者を目指す娘が、自分に宿った不思議な力を生かし、絡み合う因縁の糸を解きほぐしていく。」。青春“時代”ミステリー!死者の姿が見えたり、死者と話せたりできるおいちが、事件を未然に防いだり、許したり許されたりする。『身体が病めば心が塞ぐ。心が傷付けば身体も具合が悪くなる。人間とはそうしたものだ。どちらの治療も難しい。』。とても読みやすく面白かった。 |
 |
両手にトカレフ
(ブレイディみかこ)
図書館29
(855)
29 |
イギリスの貧困家庭の少女ミアと100年前に実在したアナーキスト金子文子の幼い頃の生き方ををシンクロさせながら物語は進む。「イギリス南東部に住む中学生のミアは母と弟との3人暮らし。母親が問題を抱えており、姉弟は食べ物にも困る日々だ。ある日図書館で、カネコフミコという日本人の自伝を手にする。生活保護のお金を薬物に遣ってしまうミアの母。まだ幼く、いじめられっ子である弟、貧しい人のためのボランティアをしており一家を気にかけてくれるゾーイ、ミアの詩をラップに乗せたいと願う音楽好きの同級生ウィルなど…。」これにフミコの自伝が差しはさまれ、物語は進行する。ヤングケアラーをテーマにしていて暗澹たる気持ちになるが、最後は光が届く。著者は修猷館高校卒で現在英国在住。 |
 |
闇医者おゑん秘録帖
-残陽の廓
(あさのあつこ)
図書館28
(854)28 |
『闇医者おゑん』シリーズ3弾!。「吉原で女郎が3人立て続けに亡くなる。美濃屋の花魁、安芸の体調を見ているおゑんに事件の依頼が。 謎の毒薬が使われていると判明する。事件の影には10年前の花魁、鈴花と討ち死にした殿様の一件が絡んでいた。
吉原に生きる女たちとおゑんの元に堕胎に送られる女たちも哀しい…」。今回は長編で淡々と話は進み少し盛り上がりに欠ける感じがしたが、やはり面白い。おゑんの感じる一つ一つに意味がある、こんな人を敵にしたら怖いだろうな。『親子であろうと夫婦であろうと幼馴染であろうと、人と人には程よい間が要る。その間は一定ではなく、取り決めがあるわけでもなく、自分たちで手探りでつかんでいかねばならない」。 |
 |
予幻
(大沢在昌)
図書館27
(853)
27 |
『ボディガード・キリ シリーズ』第三弾!「フィクサー睦月からのキリへの依頼は、女子大生岡崎紅火の警護。なにやらこの女子大生理由ありとみえ、睦月がよこした女性ボディガード・弥生とキリがタッグを組んでも、紅火はさらわれてしまう。弥生と2人で紅火を捜すキリ。そこへ誘拐の容疑者が殺害され、公安の刑事が登場したり…」。ちょいと登場人物が多く“誰だったけ?”と思ったりもするが面白くて500ページを超える長編でも一気読み。謎の中国人やアメリカのスパイも絡んでドンパチ、『新宿鮫』とは趣の違うシリーズ。『信用ができないという点では政治家は極道よりタチが悪い。極道は少なくともメンツを大事にするが政治家は保身のためなら、官僚も極道も平気で利用し、切り捨てる。』 |
 |
殺人現場は雲の上
(東野圭吾)
図書館26
(852)
26 |
“空”編。今回は軽いタッチの7つの短編からなる、1989年の作品。飛行機に搭乗する様々な人々が巻き込まれる事件を描いている。「新日本航空のスチュワーデスのA子(東大中退の美人)と太り気味で養成所では成績びりのB子の二人が、飛行機に搭乗した人物にかかわるいろんな事件を解決していく、その中で様々な人間関係や秘密が明らかになっていく」。今回も少し物足りない感じはするが今は大御所の著者、初期の頃からいろんなアイデアが満載だったんだなと想像がつく。二人の凸凹コンビのスチュワーデスのキャラが面白い。ユーモア笑推理小説、暇つぶしにはもってこい! |
 |
11文字の殺人
(東野圭吾)
図書館25
(851)
25 |
1987年著者の初期の作品、新聞に『東野圭吾がおくる“空”と“海”のミステリー』と紹介があった“海”編。「主人公の恋人が殺された。彼は生前、『誰かが命を狙っている』と漏らしていた。女流推理作家のあたしは、彼の自宅から大切な資料が盗まれたと気付き、彼が参加したクルーズ旅行のメンバーを調べる。しかしこれを皮切りに1年前の海難事故にまつわる連続殺人が起きる。」。タイトルの11文字は『無人島より殺意をこめて』と犯人からのメッセージ。映画化もされていたようで、昭和の時代では面白かったと思われる。携帯電話のない時代、こうだったんだろうな。初期作品で読みやすさは抜群だが、少し物足りなさを感じた。次は“空”編に挑戦。 |
 |
ひとりでカラカサさしてゆく
(江國香織)
図書館24
(850)
24 |
久しぶりに読んだ江國香織、彼女らしい物語。「大晦日の夜、ホテルに集った80代三人の男女。若い頃からの仲である彼らは、酒を片手に尽きない思い出話に耽り、それから、猟銃で命を絶った…。まさか、一体、なぜ。突拍子もない死を突き付けられた子や孫、友人たちの日常や記憶が交ざり合い、故人の生涯も浮かび上がっていく。」。自殺した当人たちや彼らとかかわった人たちのいろんな暮らしぶりや思いが細かく描かれている。切なくもあり、そうだろうなとも思える。ただ、目まぐるしく視点が変わるため誰だったけと混乱し読みづらかった。アンデルセンがダークサイドの人だったとか(みにくいアヒルの子、人魚姫など)、また『雨降りお月さん』はお月さんがお嫁に行く歌だと思っていた? |
 |
偽装同盟
(佐々木譲)
図書館23
(849)
23 |
『帝国の弔砲』 『抵抗都市』に続く改変歴史警察小説。「日露戦争終結から12年たった大正6年。敗戦国の日本は外交権と軍事権を失い、ロシア軍の駐屯を許していた。3月、警視庁の新堂は連続強盗事件の容疑者を捕らえるが、身柄をロシアの日本統監府保安課に奪われてしまう。新たに女性殺害事件の捜査に投入された新堂だったがこちらにもロシア軍人の影が・・・。時を同じくして、ロシア首都での大規模な騒擾が伝えられる」。東京のど真ん中にロシアの統監府が置かれている(それに、クロパトキン通りやプーシキン通りなど読んでいて変な感じになってくる)、属国こなったらこんなことになるんだろうな。街並みや建物景観の説明が多過ぎて少しだれてしまった。 |
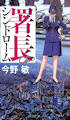 |
署長シンドローム
(今野 敏)
図書館22
(848)
22 |
「『隠蔽捜査』でおなじみの竜崎が大森署を去り、後任として、美貌のキャリア女性署長・藍本小百合がやってきた。ある日、管轄内の羽田沖海上にて、武器と麻薬の密輸取引が行われるという知らせが入るー、テロの可能性も否定できない、事件が事件を呼ぶ国際的な事件に隣の所轄や警視庁、さらには厚労省に海上保安庁まで乗り出してきて…。新署長の手腕や、如何に?」。軽い軽いノリで笑いながらアッという間に読んだ。超美人の発言で男どもが転がされる展開がとても面白い、男がいかに美人に弱いか、こんな署長がいたらいいだろうな。『外国人ギャングの問題は、難民政策、移民政策の不備が生み出したとも言えるるのだが、その背景には古来日本人が持つ差別意識がある』。 |
 |
希望のゆくえ
(寺地はるな)
図書館21
(847)
21 |
『著者は人間の心の奥にあるものをむきだしにする作家だ』と解説にあったがあまりにも人の心の闇を描いていている感じがして登場人物たちに感情移入ができなかった。「誰からも愛された弟には、誰も知らない秘密があった。突然姿を消した弟、希望(のぞむ)。行方を追う兄の誠実(まさみ)は、関係者の語る姿を通し弟の持つ複数の顔を知る。本当の希望はどこにいるのか。記憶を辿るうち、誠実もまた目をそらしてきた感情と向き合うこととなる…。」。内容の濃い物語だが私には何だかしっくりこなかった。『自分で自分のことを分かる人などいないのではないか。絶えず自分のことを見ないふりをして生きてきて、他人から見える自分に寄り添うのは苦しい。寄り添わなければなお怖い』。 |
 |
三千円の使いかた
(原田ひ香)
図書館20
(846)
20 |
お金にまつわる“節約”家族小説。「就職して理想の一人暮らしをはじめた美帆(貯金三十万)。結婚前は証券会社勤務だった姉・真帆(貯金六百万)。習い事に熱心で向上心の高い母・智子(貯金百万弱)。そして夫の遺産一千万円を持っている祖母・琴子。御厨家の女性たちは人生の節目とピンチを乗り越えるため、お金をどう貯めて、どう使うのか?」。女性はこんなにも日々の生活に一生懸命なのに男たちは切実感がない。いろいろ考えさせらることがたくさん。『人生はどうにもならないことがたくさん、例えば年齢、病気、性別、時間・・。お金や節約は、人が幸せになるためのもの。それが目的になったらいけない」。結論は“人と比べないこと、自分の人生には自分で責任を取ること”。 |
 |
刑事弁護人
(薬丸 岳)
図書館19
(845)
19 |
500ページを超える長編なのに、全く飽きさせない。この著者は3冊目だがズシリと心に響く。「ある事情から刑事弁護に使命感を抱く持月凛子が当番弁護士に指名されたのは、埼玉県警の現役女性警察官・垂水涼香が起こしたホスト殺人事件。凛子は同じ事務所の西と弁護にあ
たるが、加害者に虚偽の供述をされた挙げ句の果て、弁護士解任を通告されてしまう。一方、西は事件の真相に辿りつつあった。」。徹底的な取材の元に書かれたというだけあって司法制度の問題も浮き彫りにされる、今の日本で司法が7正しく行われているのか?
『被疑者や被告人には弁護人以外に誰も味方はいない、罪を犯すまでに追い詰められた人のほとんどは信頼を寄せられる家族や知人はいない、だから・・。』。 |
 |
あきらめません!
(垣谷美雨)
図書館18
(844)
18 |
この本は世の中の全議員、市議も県議も国会議員も、みんなに読んでほしい。「定年を迎え、悠々自適なセカンドライフを送るつもりだった郁子は、突如、夫の実家に移住ことに…。気持ちを切り替え、田舎暮らしを楽しもうとしていた矢先、なぜか市議会議員に立候補することに!」。今の世の中仕方がないと思っている人、選挙に興味ない人に喝を入れる一冊!それにしても前近代的なジーサン達には心底辟易する(この著者の本にはよく登場する)、自分も気をつけなくては。特に女性が読むと納得することばかり、ぜひお読みください。漫画のような展開ながら気分がスカッとする。『一人では何もできないが、一人でも始めなければいけない』。“後家楽”という言葉を知っていますか? |
 |
ひまわり
(新川帆立)
図書館17
(843)
17 |
33歳で事故に遭い、首から下が動かなくなった身で弁護士を目指すことを決意した女性の奮闘を描く。「突然の事故で頸髄損傷を負うひまり。復職のため壮絶なリハビリを始めるが障壁だらけ…。元の職場に復帰が叶わず、司法試験を受けるべくロースクールへ通うひまりが、家族やヘルパーのヒカル、同じ司法試験を目指す美咲、幼馴染みのレオと共に『前例のない』ことに立ち向かう…」。リハビリの様子が詳細に描いてありこんなに大変なこと何だと認識させられた。実際にモデルになった弁護士の人はいるようだが、これは全くのフィクション、重い話しながら落ち込まずに読める。ラストは涙!すごく元気がでる本。自分の手で頭を掻けるだけでも幸せです。 |
 |
迷惑な終活
(内館牧子)
図書館16
(842)
16 |
『終わった人』『すぐ死ぬんだから』などの“高齢者小説“第5弾!「年金暮らしの原夫妻(75歳、71歳)。妻の礼子はいわゆる終活に熱心だが、夫の英太は『生きているうちに死の準備はしない』という主義だ。そんな英太があるきっかけから終活をしようと思い立つ。それは家族や他人のためではなく、自分の人生にケリをつけること。彼は周囲にあきれられながらも高校時代の純愛の相手に会うため動き始める。やがて、この終活が思わぬ事態を引き起こしていく…。」。さすが、高齢者シリーズ、著者が1948年生まれということもあり、なかなかよくわかっている。“終活”って必要かな?(後に迷惑かけに程度でいいのかも…)『終活を避けるのは、生活に“死”を入れたくない。死について考えたくない』。 |
 |
ドヴォルザークに染まるころ
(町田そのこ)
図書館15
(841)
15 |
遠き山に日は落ちて…。廃校が決まった田舎町の小さな小学校。町をあげての最後の秋祭りが行われる。その小学校に関わった人達の5つの話。「小学生のとき、担任の先生と町の外からやって来た男が駆け落ちしたのを忘れられない主婦。東京でバツイチ子持ちの恋人との関係に寂しさを覚える看護師。認知症の義母に夫とのセックスレスの悩みを打ち明ける管理栄養士。父と離婚した母が迎えに来て、まもなく転校することになる小六の女の子。発達障害のある娘を一人で育てるシングルマザー。」。地方の閉塞感や自分勝手な男たちの間でそれぞれの人生を自分らしく懸命に生きる女性たち。冒頭、衝撃の一文から始まるが、最後はドヴォルザークの家路が聞こえてくるようで郷愁を誘う。 |
 |
人魚が逃げた
(青山美智子)
図書館14
(840)
14 |
アンデルセンの『人魚姫』の王子が銀座に現れた?メルヘンの世界と現実の世界が織り混ざった心温まる五つのお話。『5人の男女が“人生の節目”を迎えていた。12歳年上の女性と交際中の元タレントの会社員、娘と買い物中の主婦、絵の蒐集にのめり込みすぎるあまり妻に離婚されたコレクターの老人、文学賞の選考結果を待つ作家、高級クラブでママとして働くホステス。」。著者の得意とするストーリー展開、やっぱりいいね~!『苦しいことがあると、どうして神はこんな試練を与えるのだと憤る。神の創作シナリオで人生を動かされていると思っていたほうが、きっと納得がいくのです』
『人と人を繋ぐのは結局、愛とか恋より、信頼と敬意なのよ』。どんなに親しくても言葉がしっかりと伝わることが大切。 |

 |
原爆裁判
アメリカの大罪を裁いた三淵嘉子
(山我浩)
図書館13
(839)
13 |
昭和30年代、被爆者が国に訴訟を提起し、原爆投下の違法性が初めて争われた“原爆裁判”。昭和38(1963年)年12月7日、東京地方裁判所は原爆投下を国際法違反と判断した…。本著は何故アメリカは原子爆弾を日本に投下したのか(まさか、実際人の住んでいるところに落としてその被害状況を見たかった?)と、朝ドラ『虎に翼』のモデルになった三淵嘉子を半生を描いている。「第1章
死の商人と呼ばれた男、第2章 原爆が投下された日、第3章 放射線との戦い、第4章 アメリカはお友達?だが、第5章 女性弁護士三淵嘉子の誕生、第6章
家庭裁判所の母、第7章 原爆裁判、第8章 三淵嘉子の終わりなき戦い、『原爆裁判』判決文』。」 読むと、あの当時、いかにアメリという国が日本(日本人)をいかに見下していたかよくわかる(最も今でもアメリカに全くものを言えないのはあの時代から進歩していないのだけど…)。戦争終結に原爆投下は意味がなかったことがわかる。
・トルーマンは『けだものと接するときにはそれをけだものとしてあつかわなければなりません』 『神は土くれで白人を造り、泥で黒人を造り、残ったものを投げたらそれが黄色人種になった』そして『私はジャップが嫌い』と言っている。
最後に『原子爆弾が広島・長崎に落とされから間もなく80年になろうとしています。その間、アメリカは、その責任を一切背負うとせず、戦争犯罪である原爆投下の実態を覆い隠す捏造を行ってきました。』
にもかかわらず、日本政府は核兵器禁止条約に参加もせずにむしろ核兵器依存を深めている。 |
 |
わたしの知る花
(町田そのこ)
図書館12
(838)
12 |
『52ヘルツのクジラたち』の町田そのこ新作。“どんなにすれ違っても、”取り返しがつかなくても、不器用で、愚かで、弱くても。そこには、ずっと、愛しかない”とコピーにあった。「犯罪者だと町で噂されていた老人が、孤独死した。部屋に残っていたのは、彼が手ずから咲かせた綺麗な“花”―。生前知り合っていた女子高生・安珠は、彼のことを調べるうちに、意外な過去を知ることになる。」。謎めいた老人をさぐるうちに愛おしい人生が見えてくる。親の言うことは聞いて当然、自分の思い通りにならない時代それでも模索しながら精一杯生きる。時代が変わって、個人が尊重される時代になっても家族の関係は様々…。始め少し入りにくかったがラストは涙!。 |
 |
水車小屋のネネ
(津村記久子)
図書館11
(837)
11 |
“日だまりのような温かい家族小説。優しい人と人のつながりに心がほっこりした気持ちでに包まれた”とあった。「身勝手な母親から逃れ、姉妹で生きることに決めた18歳の理佐と8歳の律。たどり着いた町で出会った、水車小屋で暮らすししゃべる鳥<ネネ>に見守られ、人生が変転…。姉妹二人が40年にわたり過ごしてきた心の奇跡。」。物語は1981年から10年刻みで進んでいくが、全体的に少し長すぎた。しゃべる鳥は“ヨウム”、すごい長寿の鳥で賢い、知らなかった。人の優しさが身に染みる一冊。『誰かに親切にしなきゃ、人生は長くて退屈なものですよ』と。 |
 |
小鳥とリムジン
(小川糸)
図書館10
(836)
10 |
著者が『思わず道で転んでしまった時、下を向いて絶望するか、上を向いて希望を探すか、それで人生は、大きく違ってくるのではないでしょうか?』と言っている。人との出会いや日常がいとおしくなる感動作とあった。「苦しい環境下の中で、人を信頼することをあきらめ、自分の人生すらもあきらめていた主人公・小鳥。父親と名乗る人物やお弁当屋の店主との出逢いによって、“人と向き合うこと”に一歩踏み出していく…」。多様性を語っているが自然と心に入ってくる。読むにつれて感情移入していき、これ以上小鳥から大切な人を奪わないで欲しいと願いながら読んでいた。『怒りとか悲しみとか不満とかって、確実に内臓に蓄積されるんだよ。そしていつか、深刻な病となった体に現れるんだ』。 |
 |
パンとペンの事件簿
(柳 広司)
図書館9
(835)
9 |
境利彦と彼の作った売文社を舞台に、さまざまな謎を解いたり秘密作戦を決行したりという連作短編。「やくざもんに襲われて気を失っている“ぼく”を救ってくれたのが堺利彦や大杉栄に荒畑寒村たち。それがきっかけで売文社に居候することになった、”ぼく”の視線で描かれる当時の社会主義たちの人たち。」
ほかに小口みち子、山崎今朝弥など実在の人物が登場し、読んでると彼らが掲げる社会主義は至極当たり前のことなのに、なぜ弾圧されないといけなかったのかと、今にも通じる理不尽さに腹が立つ。『金儲けのためなら平気で人殺しの武器を作り、それを売り、若い人たちを戦場に送って殺し合いをさせて、新たに戦争を始めることさえ辞さない。すべて金儲けのためだ』。 |
 |
テスカトリポカ
(佐藤究)
図書館8
(834)
8 |
暴力の嵐に臓器売買が絡まる目を背けたくなる物語、これが直木賞と山本周五郎賞を受賞している.。「メキシコのカルテルに君臨した麻薬密売人のバルミロは、対立組織との抗争の果てに海外に逃走、潜伏先のジャカルタで日本人の臓器ブローカーと出会う。二人は新たな臓器ビジネスを実現させるため日本へと向かう・・・」
宮部みゆきが『麻薬という呪いと、血と生贄を求める古代の神々。想像を絶する激しい暴力の果てに現れる血肉を備えた神の姿。登場人物ほぼ全員悪党なのに、奇妙な愛嬌とユーモアがあって、恐ろしいのに魅力的だ』
と言っているが、私には苦痛に満ちた展開で、途中で何回かやめようと思ったが、ただ結末が気になりやめられなかった。う~ん、二回目も同じ感想。 |
 |
ツミデミック
(一穂ミチ)
図書館7
(833)
7 |
新型コロナウイルス感染症のパンデミックを背景に、罪とパンデミック(ツミデミック)を掛け合わせた言葉で、コロナ禍の日常で起こったさまざまな『罪』をテーマに六つのお話。「違う羽の鳥:中学の時に電車に飛び込んだ同級生が大学生になった優斗の前にあらわれた。
ロマンス:デリバリーのハンサム配達員を求めて破滅していく主婦。 憐光:15年前の豪雨に流されて死んだ女子高生の幽霊。特別縁故者:コロナで職を失った料理人、近所の老人との交わりで人生が好転。祝福の歌:女子高校生の娘の妊娠。さざなみドライブ:自殺志願者達のドライブ。」。など緊急事態宣言の中、ちょいと怖い話。未知のウイルスも怖いが一番怖いのはやっぱり人間。 |
 |
QJKJQ
(佐藤究)
図書館6
(832)
6 |
朝日新聞文芸欄に『純文学から転身 大逆転』と、江戸川乱歩賞受賞作ということで読んだ。選考委員の湊かなえが高い評価をつけながらも“こういう作品があまり好きではない”と書いていたが私も同じ感想。「猟奇殺人鬼一家の長女として育った17歳の亜李亜。一家は秘密を共有しながらひっそりと暮らしていたが、ある日、兄の惨殺死体を発見してしまう。直後に母も姿を消し、亜李亜は父と取り残されて…。」。著者が“j残酷だけど陰惨でない描写を心がけ”といっているが、やはりどうも…。謎が精神分析と脳科学の視点から解き明かされるというのには興味をひかれたがわかりにくかった。『武力行使が許されるのは国の仕事についている人間だけなのさ。警察官、機動隊、自衛隊、特殊部隊…」。 |
 |
90前後で、女性はこう変わる
(樋口恵子)
(下重暁子)
図書館5
(831)5 |
92歳の樋口恵子さんと、88歳の下重暁子さんの心と体の変化についての対談集。男性が読んでも納得!「『運動をして筋肉を落とさないようにするほうがいい』わかっていても、簡単にできないのが人間です。『何もないところで、ふゎ~っと転ぶ。転倒適齢期をいかに生き抜く?和式トイレで立ち上がれない!『老いるショック』は75歳。女性は75歳が老いの分かれ目」などなど。『75歳を境に衰えを感じて外出を控えたりと行動の範囲を狭くした人は急速に元気がなくなっていく』『どうでもいいことに怒らない。そしてたいていのことは許す。バカな喧嘩は売られても買わない。』『住み慣れた場所から離れ、友人も知人もいない場所に引っ越すのは負担が大きく、場合によっては老人性うつのきっかけにもなる』。 |
 |
光のしるべ
えにし屋春秋
図書館4
(830)
4 |
縁を商いとする者と頼る者の光と影を描く<えにし屋春秋>シリーズ第2作。「身寄りのない子どもたちと暮らす孤児・信太。物乞い稼業で糊口をしのぐ毎日だ。だが、どうしても実入りのなかった日、信太は一緒に物乞いをするおみきさんに連れられ、〈えにし屋〉を訪ねる。信太たちを出迎えたのは、お初という妖しくも美しい女。一方同じ頃、三十路を過ぎと見える、やけに疲れ果てた夫婦もお初を訪ねていた。」。やはり面白かった、色々な嘘や商家の嫁の立場、まさかのたくさんの裏切りそして親子の愛情といろんな思惑が絡んで読み始めたらやめられない。第一作目でお初の正体が明かされるので、読んでいない人は一話から読んだ方がいい。 |
 |
坂の中のまち
(中島京子)
図書館3
(829)
3 |
文豪ひしめく坂だらけの町の不思議な恋のお話。「坂中真智は大学進学を期に富山から上京する。下宿先は祖母の親友である志桜里さん(彼女には重大な秘密があった)の家。坂にやたらと詳しい志桜里さんからレクチャーを受け、憑依型文学青年のエイフクさんと歩き回り、幽霊?に会ったり、不思議な夢を見たり、面白い体験に出くわす。」。“江戸川乱歩『D坂殺人の別解?”“遠藤周作『沈黙』の切支丹屋敷に埋まる骨が語ること”“安部公房『鞄』を再現する男との邂逅”“夏目漱石『こころ』みたいな三角関係”など文京区の坂を舞台に語られる六つのお話についついのめりこんでしまう。読みやすくほんわかなる本。坂がたくさん出てるので地図があったらいいのに…。 |
 |
リハーサル
(五十嵐貴久)
図書館2
(828)
2 |
“こんな話を書く人の神経を疑う、主人公の危機管理意識の低さは異常だ、あんな女がいるはずない。”と、ある読者が言っていたがまさにその通り読まなければよかったと思う話(一種のホラー小説)、それでもラストが気になり読んでしまった。「花山病院の副院長・大矢は、簡単なオペでのミスを新任の看護婦・リカに指摘され、“隠蔽"してしまう。それ以来、リカの異様な付き纏いに悩まされる。一方、病院内では婦長の転落を始め陰惨な事故・事件が続発そして、大矢の美しき婚約者・真由美が消えた。」。『肉体の衰えがある種の被害妄想に転化し、危害を加えられるのではないかと・・・。その怯えが怒りに変わるというのは高齢者にはある。』など、後味のいい本ではなかった。 |
 |
罪名、一万年愛す
(吉田修一)
図書館1
(827)
1 |
残された昭和の名作映画『砂の器』『飢餓海峡』『人間の証明』が謎解きの一つのヒントになる。「探偵・遠刈田蘭平は富豪一族の三代目・梅田豊大から時価35億円の宝石“一万年愛す”の捜索を依頼される。創業者・梅田壮吾の米寿の祝いのため、蘭平は長崎の句九十九島の孤島を訪れることに…。」。奇想天外な話ではあるが、上野駅で暮らしていた戦争孤児たちの回想シーンは胸が締め付けられる。ミステリーの要素を持った家族愛の物語という感じ?『悪人』や『路(ルウ』を書いた著書者とは思えないが後半は俄然面白くなる。
タイトルの『一万年愛す』というルビーが大切な役割を担っている。 |